道路位置指定の概要
道路とは
市街地における道路は、単に通行のためだけでなく、災害時における避難や防災等の役割をはたしています。
建築基準法(以下「法」という)上の「道路」とは、法第42条第1項の規定で原則として幅員4m以上のものとしています。
ただし、下記の法第42条第2項( 6 )の場合のように、一定の要件を満たしている道については、道路とみなす場合があります。
建築基準法(以下「法」という)上の「道路」とは、法第42条第1項の規定で原則として幅員4m以上のものとしています。
ただし、下記の法第42条第2項( 6 )の場合のように、一定の要件を満たしている道については、道路とみなす場合があります。
建築基準法の「道路」
- 国道、県道及び市道などの道路法による幅員4メートル以上の道路(法第42条第1項第1号)
- 開発行為や土地区画整理事業などにより造られた幅員4メートル以上の道路(法第42条第1項第2号)
- 建築基準法施行(昭和25年11月23日)の際に既に存在した幅員4メートル以上の道(法第42条第1項第3号)
- 市道整備、都市計画事業及び土地区画整理事業などの事業計画のある道路で、2年以内にその事業が予定されている物(法第42条第1項第4号)
- 道路の位置の指定を受けたもので幅員4メートル以上のもの(法第42条第1項第5号‐道路の位置の指定)
- 現在、幅員が4メートル未満であるが、法施行の際にその道に沿って家が建ち並んでいた幅員1.8メートル以上の道路(法第42条第2項の道路といい、原則として道路中心線から両端に2メートル後退した線を道路境界線とみなします。)
道路と敷地の関係
建築物の敷地は、一般的に建築基準法の道路(幅員4メートル以上)に2メートル以上接していなければなりません。(法第43条第1項)
ただし、専用通路の路地状の部分の長さが15メートルを越える場合には、平塚市建築基準条例によりその路地状部分の幅員を3メートル以上とする必要があります。
また、共同住宅、大規模店舗や映画館などの特殊な建物の場合は、同条例によりその規模に応じて、避難のための通路や出口の確保のため、敷地が道路に接する長さや敷地内通路の幅員の規定が設けられています。
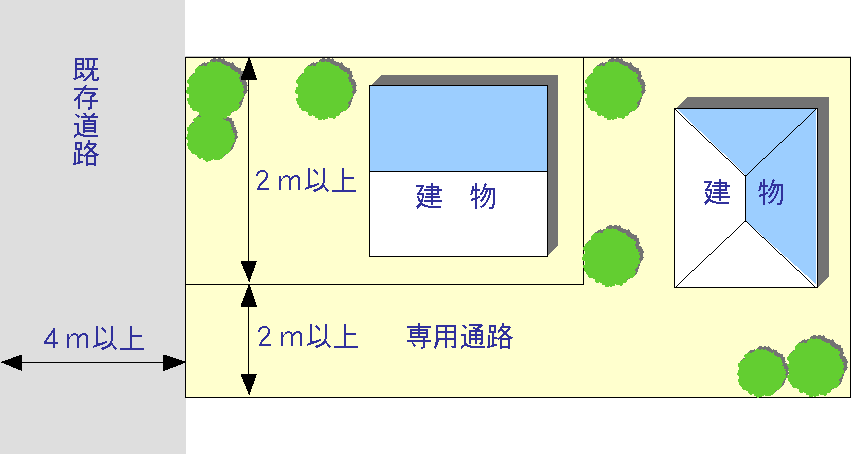
ただし、専用通路の路地状の部分の長さが15メートルを越える場合には、平塚市建築基準条例によりその路地状部分の幅員を3メートル以上とする必要があります。
また、共同住宅、大規模店舗や映画館などの特殊な建物の場合は、同条例によりその規模に応じて、避難のための通路や出口の確保のため、敷地が道路に接する長さや敷地内通路の幅員の規定が設けられています。
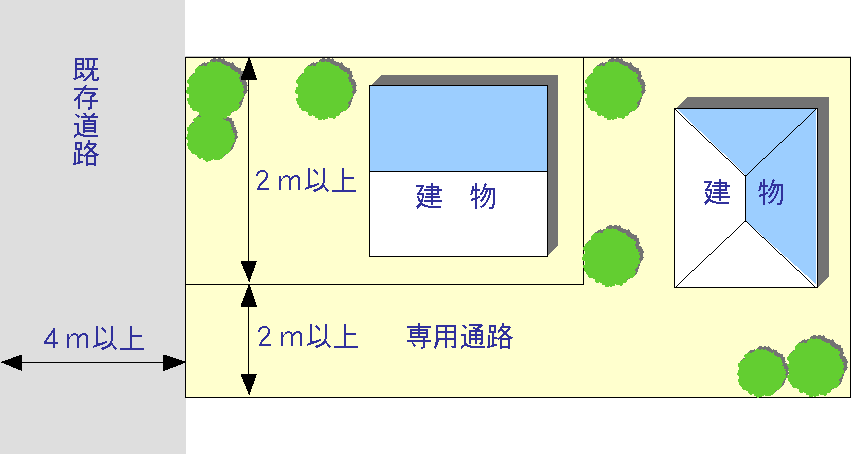
道路の位置の指定とは
専用通路は敷地の一部であり、それぞれの敷地が道路に2メートル以上接していなければ、既に建っている家の増築や改築等ができなくなります。
また、新たに宅地を造成する場合、それぞれの宅地は道路に2メートル以上接していなければなりません。造成区域の規模が市街化区域内で500平方メートル以上の場合には、都市計画法による開発許可を得て道路を造ることとなりますが、500平方メートル未満の場合に限り道路(私道)を造る際は、道路の位置の指定を受けなければなりません。
道路の位置の指定にあっては、幅員や形状、排水施設等、道路として具体的な基準によって整備する必要があり、また、道路となるべき部分の土地等の権利者の承諾が必要となります。
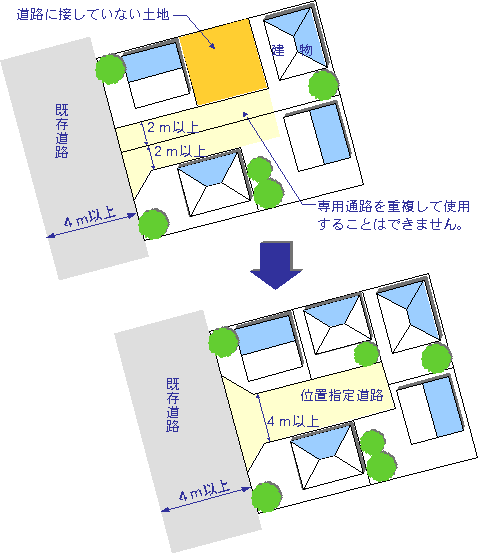
定められているほか、本市の「道路位置指定申請の手引き」の技術基準に従って整備していただきます。
また、新たに宅地を造成する場合、それぞれの宅地は道路に2メートル以上接していなければなりません。造成区域の規模が市街化区域内で500平方メートル以上の場合には、都市計画法による開発許可を得て道路を造ることとなりますが、500平方メートル未満の場合に限り道路(私道)を造る際は、道路の位置の指定を受けなければなりません。
道路の位置の指定にあっては、幅員や形状、排水施設等、道路として具体的な基準によって整備する必要があり、また、道路となるべき部分の土地等の権利者の承諾が必要となります。
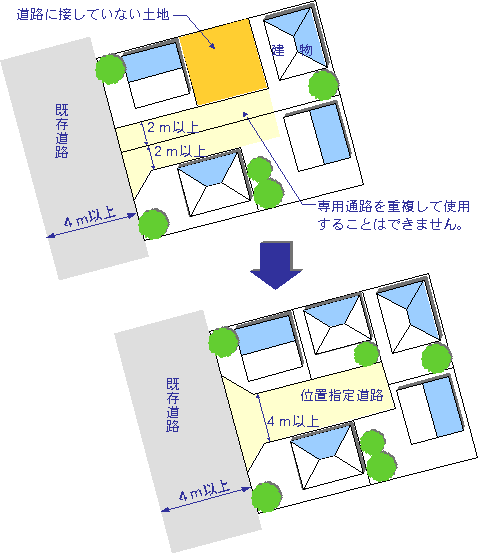
定められているほか、本市の「道路位置指定申請の手引き」の技術基準に従って整備していただきます。
主な技術基準
- 角地の隅角をはさむ辺の長さ2メートル以上の隅切りを設ける。(片隅切りの場合は辺の長さ3メートル以上)
- 位置の表示は区域をコンクリート製の側溝、縁石等で行う。
- 表層は原則としてアスファルト舗装以上とする。
- 縦断勾配は原則として9パーセント以下とする。
- 横断勾配は原則として1パーセント以上、2パーセント以下とする。
- 排水に必要な側溝、街渠等を設ける。
(詳細は「道路位置指定申請の手引き」の技術基準をご参照ください。)
申請手続きの流れ
1.事前相談
- 窓口相談は建築指導課で行います。
- 窓口相談後、「事前相談書」を提出していただき、計画内容の適合性を審査します。
2.本申請
- 事前相談の結果、「申請書」を提出していただきます。
- 提出図書や関係権利者の承諾書の書類審査を行います。
3.工事着手
- 書類審査終了後、工事を着手してください。
4.完了検査
- 道路の築造工事完了後、完了検査を行います。
5.道路の位置の指定の告示
- 検査に合格すると、指定の告示を行います。
6.指定の通知
- 指定の通知書を交付します。
7.建築計画等
- 建築確認申請に移行します。
申請の手引き
- 申請手続きや技術基準等の詳細について、「道路位置指定申請の手引き」に記載しています。
PDF形式でダウンロードできますのでご利用ください。
- 申請様式は、WORD形式又はPDF形式で申請様式1からダウンロードできます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ先
建築指導課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-9731(建築指導担当) /0463-21-9732(建築審査担当)/0463-20-8860(建築安全担当)
ファクス番号:0463-21-9769


